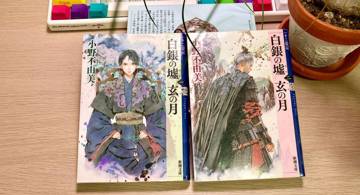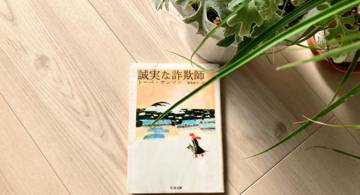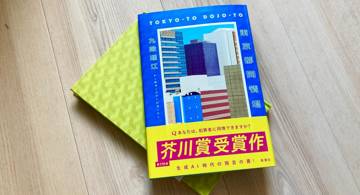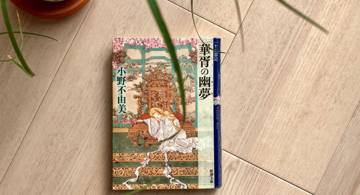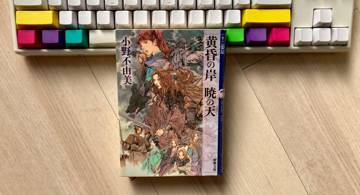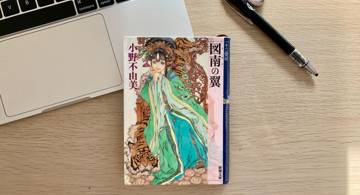概要
年末年始読書をやっていこうぜ。前回の続き。
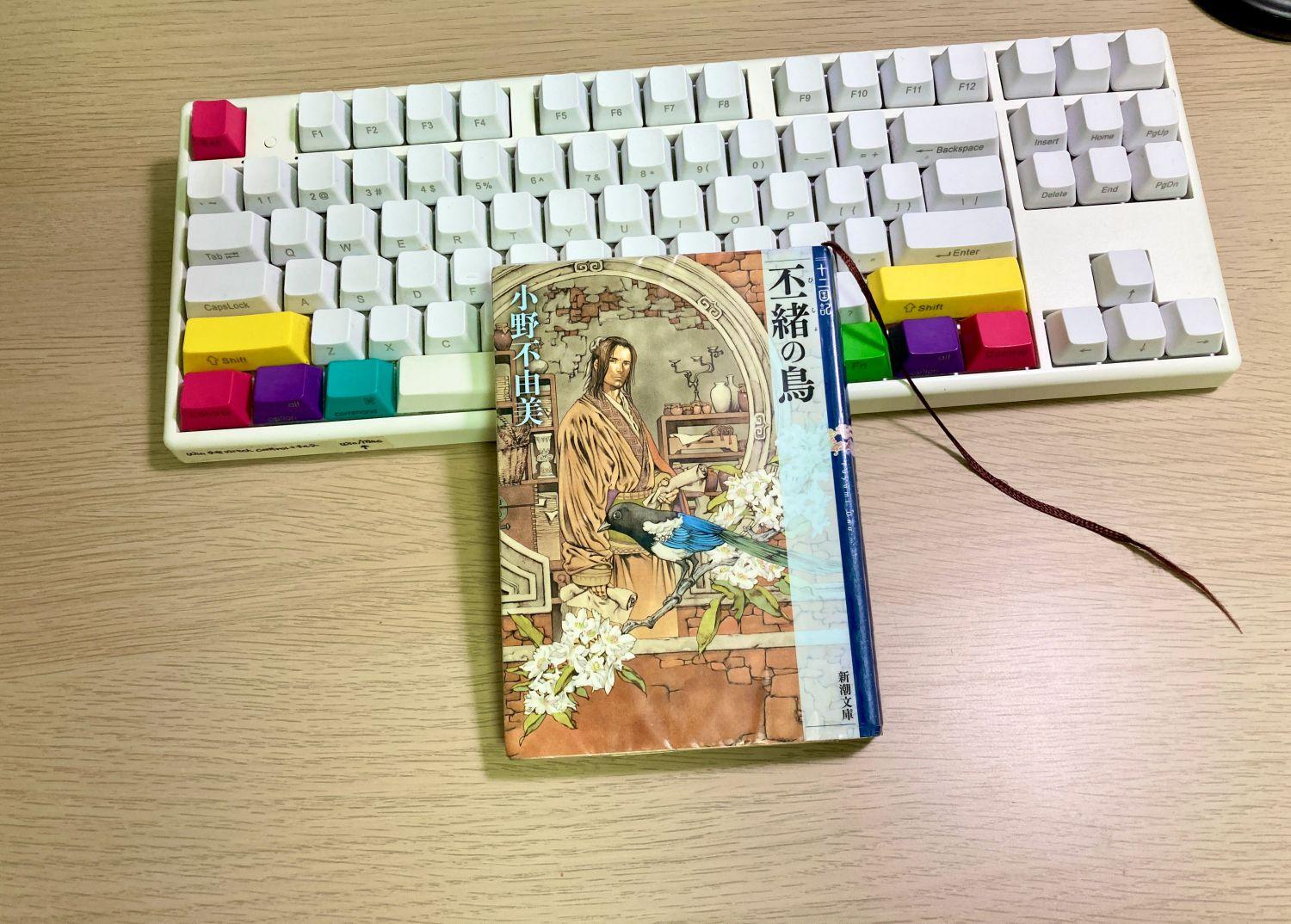
……というか今回も短編集だった。前回に引き続き、軽くサマリと所感を書く。
サマリ
丕緒の鳥
- 羅氏という職務がある。祭祀吉礼の催しのひとつ、大射で使う、陶鵲 (トウシャク) を作る部署のトップだ。ああもう、用語が多すぎるよ。大射がクレー射撃みたいなもんで、陶鵲が射撃の対象である皿だ。
- 羅氏の丕緒 (ヒショ) さんは落ち込んでいた。だって歴代のアホ王 (慶国の俐王、薄王、比王、予王) たちはアホばっかりで、陶鵲へ込めた丕緒の思いをまったく理解しないからだ。彼は、陶鵲を通じて、王に民を思う気持ちを持って欲しいのだ。
- そこで、過去の同僚である蕭蘭 (ショウラン) のことを思い出す。彼女は悪政の現実から目を逸らしているように見えて、丕緒さんはあんまり好きじゃなかったのだ。が、考えてみれば彼女は現実と正面から向き合う人ではなかったが、現実を拒む人ではなかった。
- そこで蕭蘭が作りたがっていた陶鵲を再現してみたところ、新王、我らが陽子さんの心をがっちり捕まえたようで、陽子さんは “胸が痛むほど美しい” と評するのだった。
落照の獄
- 司刑という職務がある。裁判長みたいな職務で、瑛庚 (エイコウ) さんが担当している。同僚の率由 (ソツユウ)、如翕 (ジョキュウ) と一緒に、とあるシリアルキラー狩獺 (しゅたつ) の審理に苦慮していた。
- 狩獺は明らかに死刑レヴェルの大悪人であり、死刑しないなんてことになれば民衆が暴動を起こすかもしれん。
- でも、柳国 (リュウコク) では “大辟 (タイヘキ; 死刑のこと) はこれを用いず” という大原則があるんだ。しかも最近国が荒れており、一度死刑の前例を作ると、国政による濫用を招くかもしれん。
- そんな苦慮に耳を貸さない瑛庚さんのバカ妻の清花 (セイカ) は、死刑に賛成で、司刑である夫のもとに犠牲者の家族を連れてきて同情を引こうとする。こいつが非常にウザい話。
青条の蘭
- 地官迹人 (チカンセキジン) という職務がある。野木の調査や収集を行って、民の役に立てる素敵な仕事だ。それをがんばる標仲 (ヒョウチュウ) くんと包荒 (ホウコウ) くんは、山毛欅 (ブナ) の木の疫病を見つける。山毛欅が石化してぶっ倒れていくのだ。山毛欅が全部倒れてしまったら、生態系が崩れ、山崩れにより農地が台無しになって、民に大きな被害が出る……。
- 彼らは頑張って解決策を何年も探し、とうとう発見する、山毛欅を治療できる、青条の蘭という草だ。
- ほんでそれを新しい王に献上して、祈願してもらうよう訴状を出す。この世界では、王が祈願すると、その植物が国中の里木に生るのだよ。
- しかし空位の時代が長いせいで腐れ官吏ばっかりで、訴状を握りつぶすわ、その薬を私欲のために利用しようとするわ、最悪な状況。標仲くんは吹雪の中、徒歩で王宮を目指し、志なかばで倒れつつも、意志をついだ人々によって青条の蘭は王の元へ届くのだった。
風信
- 慶国の色ボケ女王、予王の時代。蓮華 (レンカ) は軍によって家族を殺されて、保章氏 (ホショウシ; 自然環境を調べて、暦を作る仕事) の園林へ身を寄せる。
- そこのみんなは、自然環境を調べることを生業としているので、浮世離れしており、蓮華にとっては現実を直視していないように見える。蓮華は “あたしはあんな大人にはならない” と苛立ちを募らせる。この幼稚な女にとっては、眼の前にある状況だけがすべてで、先を見据えた研究の価値が理解できないのだ。
- たまたま学者の支僑 (シキョウ) さんが、その学術知識によって、街の人々を慰めるところを目にして、蓮華は研究の価値を感じる。が、結局眼の前で利益が発生しないと理解できないのは変わらない。
所感
- なんだよ蕭蘭の漢字! と腹を立てながら調べたら、蕭ってヨモギなのかよ! それを知ると、蓬髪の女性のビジュアルがなんとなく浮かんでくるな。
- ぼくらがこれまで読んできた十二国記は、大抵は王たちを主役とした話だ。今回は、一般の人々へフォーカスした、しかも王様の居ない、空位の時代の話だった。ぼくら読者にとっては王が居るのが当然だったが、空位の時代はこんなに悲惨なんだぞ、ということを教えてくれる巻だった。十二国記への理解がぐっと深まる1冊だったね。
- 陽子さんに対して丕緒さんが “飾り気もなく率直” “この王なら、不吉と言って拒んだりすまい” と感じるところはちょっと涙ぐんでしまった。特段共感するような話ではなかったのだけれど、優れた筆致によるものだろうか。
- 王様たちが出てこないので、なんちゅーか普通の面白い小説を読んでいる気分になっちゃった……。主要な連中が出てこない話がこんなに奥深いのだから、小野不由美さんはすごいよな。