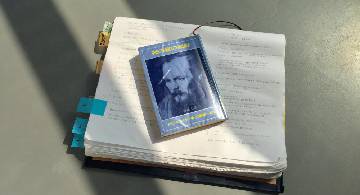概要
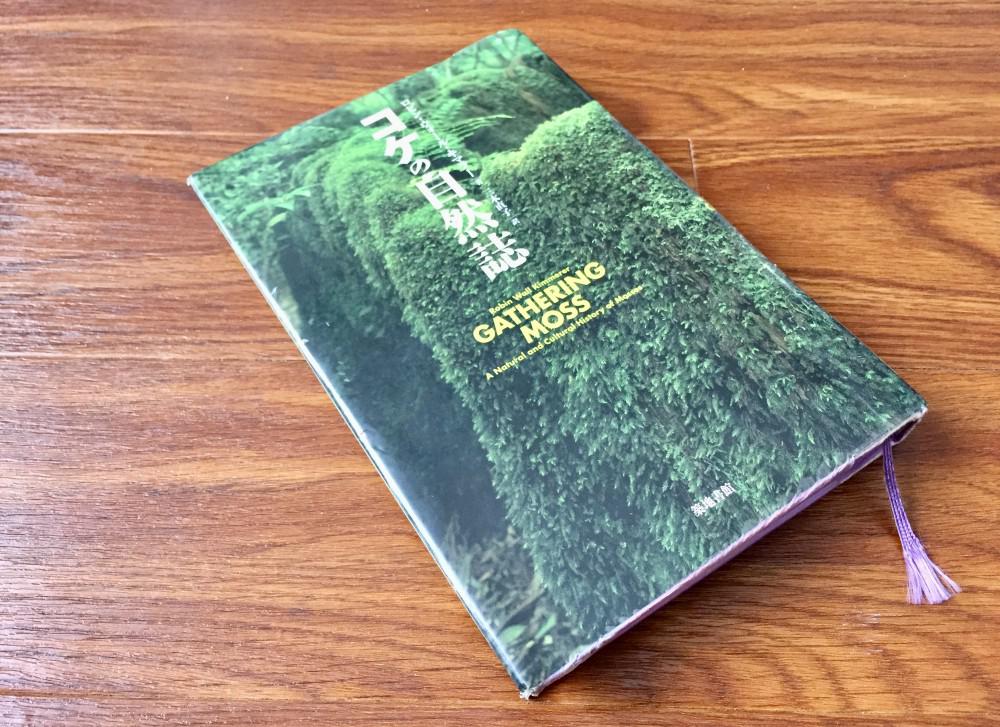
原題『GATHERING MOSS』。
知人からおすすめされたので読んだ。簡単なサマリと感想を書く。
サマリ
これはコケ学者さんのエッセイだ。コケの生態、生活環の解説に始まり、さまざまなコケの特徴をエッセイ風に紹介してくれる。さらに著者の学者としての活動内容を描写した章もあり、植物学者のフィールドワークがどんなものなのかその一端を垣間見ることができた。
エッセイということでサマリが難しいんで、楽しめた箇所を箇条書きして残しておくよ。まずはコケのうんちく。
- コケは「変水性」をもつ。乾いても、水が戻れば回復する特性のこと。コケにとって光は水ほど重要ではない。だからコケの葉は木の葉とは違って、水を溜めやすい形をしている。
- ミズゴケは、自分の体重の20〜40倍の水を吸収する。これは紙おむつの吸収力にもひけをとらない。土着の民族はこのコケをおむつや生理用ナプキンとして使っていた。
- ミズゴケは湿地に生えて、自らの生育環境を操作する。水を保持して嫌気性の発根環境をつくることで、微生物は繁殖しづらくなる。そのせいで養分の再利用がされないから、湿原は栄養不足になり、背の高い維管束植物が排除されるというわけ。
- 着生蘚苔類はチャクセイセンタイルイと読む。(読めなかった)
- コケを食べる生物は皆無に近い。コケの繊維は消化不可能だからかもしれない。
森のうんちく。
- 嵐や火事といった撹乱があったあとの森にはさまざまなギャップが生じる。土壌の露出とか、倒れた木の跡など。それらのギャップはそこに適合する植物が埋める。そうやって森が構成されることを「ギャップ動態」という。筆者にはそれが物事の仕組みの秩序と調和を象徴しているようにみえる。
- 木の幹を流れ落ちる水を「樹幹流下」といい、木の枝や葉から滴り落ちる水を「通過流」という。こういった雨水が木を洗浄し、養分を根に届ける。
コケと都市。
- コケの葉は肺胞とよく似ていて、濡れていないと機能しない。この水の膜は二酸化硫黄が触れると硫酸に変化する。クルマの排気ガスの亜酸化窒素が触れれば硝酸に変化する。他の植物と違ってクチクラで護られていないコケの葉は、それで死んでしまう。
- だから、コケは都市にとっての炭鉱のカナリアになる。コケのない街は、空気が汚染されている。
- 筆者はよく都市の人々から、コケを排除したいという相談を受ける。芝生がコケに侵食され、枯れているというらしい。しかしコケには芝生と競争して勝つ能力は備わっていない。そういう場合、その土地が、コケの成長に適し、芝生の成長に適していないだけ。
- 屋根に生えたコケを除去したがる人もいる。しかしコケは屋根板を日差しから守り、ヒビが入ったり反ったりするのを防ぐ。夏には冷却層となるし、雨水が流れ落ちるのをゆっくりにする。なのに都市では、コケの生えた屋根は道徳的な退廃を象徴しているとされるらしい。そんな倫理観はあべこべである。
ネイティブ・アメリカンのおしえ。
- 生き物がもつ、それぞれ特有の才能や知恵は、創造主から最初の指示として与えられたものである。それを手段として互いのために尽くすことがすべての生き物の責任なのだ。
- 植物は、必要とされるときに現れる。そして尊敬されている限り、彼らは私たちのもとに留まる。私たちが彼らのことを忘れれば、彼らはいなくなってしまう。
コケ学者の仕事。
- ヨツバゴケとヒメカモジゴケの繁殖戦略を調査する筆者。ヨツバゴケはアスペンの木に教わったかのように、非常に拡散しやすい胚芽をたくさん送り出す。ヒメカモジゴケはキハダカンバに似ており、もっとも小さなギャップに飛びついて生き残る。ヨツバゴケの大きなギャップは倒木の横側にあり、ヒメカモジゴケのそれは倒木の上面にある。その規則性は何が作り出すのか?
- この章はまるでミステリ小説を読んでいるかのようなワクワク感をくれた。
- 謎の大金持ちが構想する、アパラチア山脈の植物相をそっくりそのまま自生植物園に復元するプロジェクトに、相談役として参加する筆者。謎の園主は金にものを言わせて大木を掘り起こして自分の土地にもってくる。美しい天然の岩肌を爆破で切り出し、クレーンで運びだす。筆者は知らずのうちに破壊のためのコンサルタント、コケの殺しの片棒をかついでしまう。しかし園主は、自分の土地に植えたコケを丁寧に守り包むために外国から専門家チームを呼び寄せたのだ。その気持ちが真摯であることは間違いない。筆者は、人は何かを所有し、同時に愛することはできないのだ、と思う。
- この章はまるでサスペンス小説だ。章の締めが素晴らしい。「園主の本当のコケ庭園はここにあったのだ」。
- コースト・レンジ山脈でコケ泥棒の破壊跡を調査する筆者。「オレゴン・グリーン・フォレスト・モス」と呼ばれる高級品を出荷するために1990年以降、オレゴンのコケは業者の標的になっている。コケが持ち去られるとき、コケに関連する様々な相互関係もそれとともに持ち去られるのだ。
感想
本の後半には、人々とコケとの関わりが記されている。それは主に、人がコケを破壊し、その背後にある自然環境を破壊していることへの警鐘だ。正味な話、ぼくはそういう構成の本が好きじゃないんだ。前半は気分良く読書をしていたのに、最後には社会問題、環境問題について考えさせてくるからだ。
だけれど一番最後にこの本は、ぼくの好みな話をもってきてくれた。ヒカリゴケの話だ。
ヒカリゴケは世界にほんのわずかなものしか……洞窟の外の光の1%、そのまた10%……求めず、それに応じて輝く。持つものはシンプルに、得るものは豊かに、というミニマリズムの手本を体現しているコケだ。筆者はその秘密の場所を大切に思っていたが、その岩壁はあるとき崩れ、洞窟を塞いでしまう。
筆者はそれを、自らの自然への敬意の欠落のせいだと捉える。筆者は家にカーテンを吊るしたばかりだった。それは湖の音や、ホワイトパインの樹脂の香りを締め出す行為だった。意味もなくパタパタとはためくカーテンは、必要なものはもうすでにここにあるということを筆者が忘れたことを表していた。オノンダガ族の年寄りがいうように、植物は、我々がそれを尊敬する限り、我々のもとに留まってくれる。だがひとたびそれを忘れれば、彼らはいなくなってしまうのだ。
そういう話、結構好きなんだよね。