概要
先日読んだ ”砂糖の世界史” を楽しめたので、同作者の本を選んでみた。ただ、今回はイマイチだったかな。
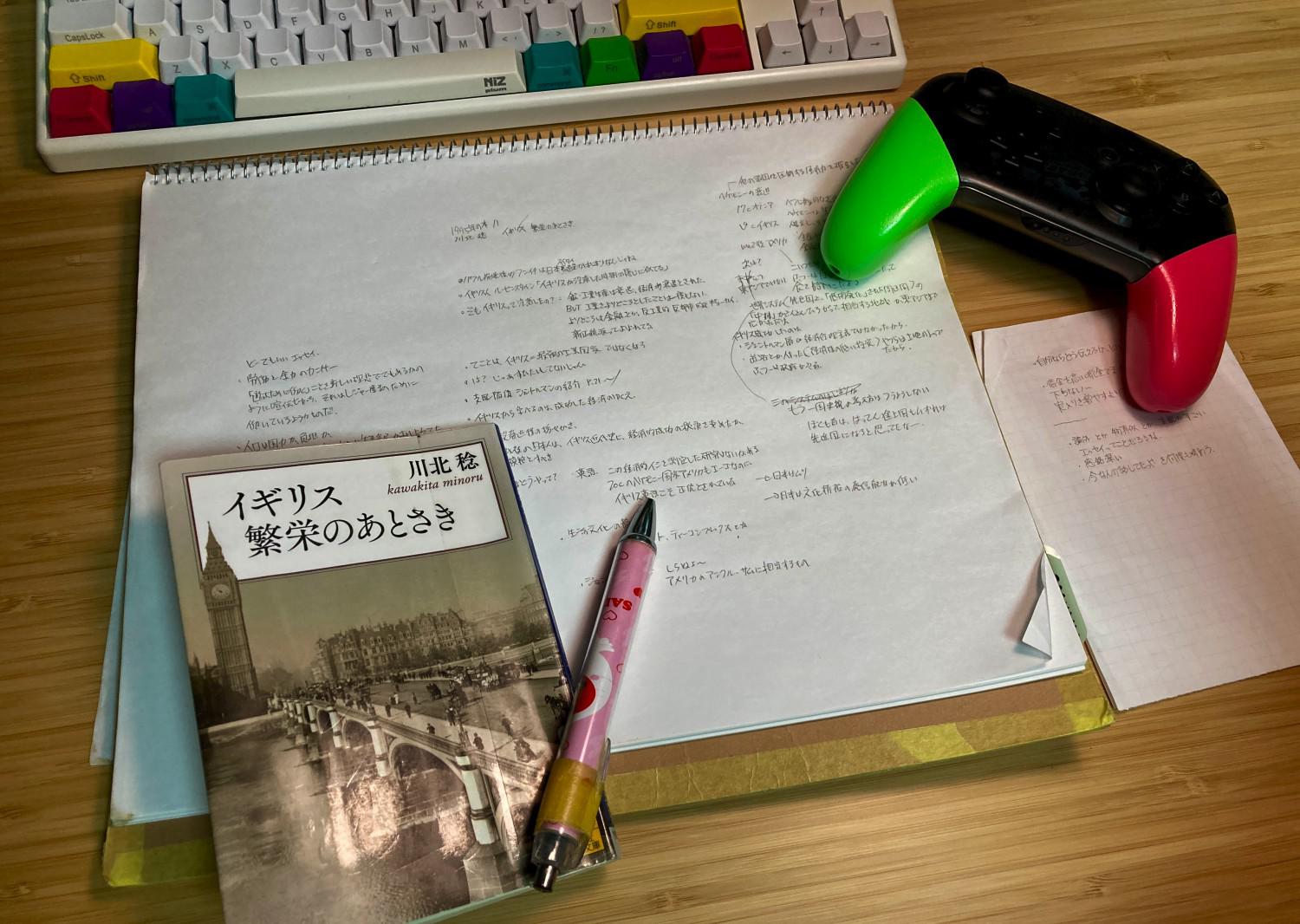
戦前戦後の日本人は、イギリス近代史に対して、経済的成功の秘訣を求めてきた (らしいよ)。でも、イギリスについてほんとうに模範とすべきは、ソコじゃないんだよ、ってことが言いたい本だった。
サマリと感想を書く。
サマリ
ぶっちゃけこんだけ↓でいい
- 日本人は、イギリスのことを、経済的成功の模範として扱ってきた。
- でもイギリスから学ぶべきなのは、その没落過程がとても緩やかな点である。
- じゃあどうして緩やかなのかっていうと、イギリスには “世界的に通じる正統な英語” と “輸出に堪える生活文化” があるからだ。
- 日本にはどっちもないから、せめて世界への輸出に堪える生活文化をこしらえたほうがいいし、文化情報の発信能力が低いと言われているのも自覚したほうがいい。でないと “ポルトガル的な役割” で終わるよ。
てかイギリスって没落してんの?
- 鉱・工業生産が衰退することが、経済の衰退とされていた。なのでその物差しで見ると、没落している。
- しかしイギリスが工業を拠り所としたことは一度もない。拠り所は金融だった。そう考えると、 “イギリス=最初の工業国家” という扱いが揺らぐ。この考え方は新正統派っていうらしい。
- 金融業界でいうと、中枢はアメリカに移っているので、イギリスは衰退している。が、工業を物差しとして考えたときほど劇的に衰退しているわけではない。
- そしてアメリカも衰退してきている。まあヘゲモニー国家は順番に衰退していくものなので。
ヘゲモニー国家って何
- 他の諸国を圧倒する経済力を確立した国のこと。
- 17cのオランダ、19cのイギリス、ww2後のアメリカである。
- ヘゲモニーは、生産、商業、金融の順番に確立し、その順に優位を喪失するものだ。
- ヘゲモニー国家は自由貿易で優位に立って、食糧を輸入に頼るもの。だが、アメリカだけは食糧自給を達成した。
- 次のヘゲモニー国家はどこか? という話になると東アジアが挙がることがあるが、そうはならない。せいぜい、世界システムの中枢がどんどん広がって、中枢に相当する地域が東アジアまで広がるくらいだ。
所感
今回はイマイチ楽しめなかったな。もちろん本の質が悪いというわけじゃなく、ぼくには合わなかったというだけだが。 “経済的成功の秘訣ではなく、成功後どう振る舞ったらよいかをイギリスに学ぼう! 具体的には生活文化の確立な!” で終わる話に、どんだけ紙面を割いてるんだよ。……というのがメインの感想になっちゃった。
その話をつねに中心に据えて話してくれればよいのに、話があっちやこっちへ飛ぶ。
- 労働と余暇の関係とか、
- “「遊ぶために働く」ことを新しい理想ででもあるかのように喧伝する輩がいるが、それはレジャー産業のために働いているようなものだ” とか、
- 人口は国力なのか、負担なのか、とか、
え? 何の話? って頻繁になった。べつに単体のコラムとして読むぶんには良いけれど、 “いま何の話してたっけ?” のオンパレードだったよ。子供のころ、眠たくなる授業って、こういう先生の授業だったなあと思い出した。こちらの理解を重視しておらず、ただセンセが話したいことを話している授業な。
もちろん楽しめた部分もあったぜ。前回読んだ『砂糖の世界史』はたいへん楽しめたことは前述したが、そっちで学んだことが、今回の読書では活きた。『砂糖の世界史』を読んでいると、
- 17cのオランダに続いて19cのイギリスがヘゲモニーを獲ったことや、
- “世界システム” という言葉の意味と、そのイメージや、
- “ポルトガル的な役割” というのがどういうものなのかとか、
- この著者はたぶんイギリス大好きなのでいつの間にかイギリスのめっちゃ細かい話になってることなど、
……がすんなりと分かって、面白い。歴史系の本を読むとき楽しいのって、こういうところなのかも。
ちなみに世界システムというのは、 “各国はそれぞれに独立して発展していくもの” “やがてはすべての国が先進国になる” という考え方に異を唱える考え方で、世界の国々は、先進国と、先進国によって “低開発化” された周辺国によって成り立っているという考え方だよ。いま思い返してみれば『砂糖の世界史』は、一冊かけて、この考え方を学ぶ本だったな。その本自体を読んでいるときよりも、別の本を読んだときにそのことが分かるというのが面白いな。
また、 “ポルトガル的な役割” ってのはだな……。ポルトガルは、ヨーロッパの中でいち早くイスラムの支配から離脱したのだが、ヘゲモニーを獲ることはなかったのだよ。なので “的な役割” というのは、その地域の勃興の先触れ的な立ち位置ってことだろう。このことも『砂糖の世界史』は良い感じに教えてくれた。ポルトガルのことを単体で教えてくれたわけではなく、イスラムの時代から近代までの流れを、 “砂糖” という中心をブレさせずに教えてくれたんだ。だから頭に残っている。
『砂糖の世界史』には “いま何の話してたっけ?” がほとんどなかった。今回の本は、その真逆。反面教師。





