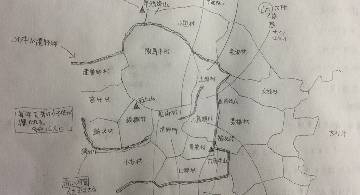●
サマリと感想を書く。
●
ヨーロッパによる武力鎮圧前のアフリカ。ウムオフィアという村に、オコンクウォさんという村一番の屈強な戦士がいた。彼はめっちゃ強くてよく働き一代で納屋をヤム芋でいっぱいにし、子供をめったに褒めず、妻たちを力で従わせる、そして「弱さ」を憎む男の中の男だ。その男らしさの背景には、ろくでなしの父親の存在があった。オコンクウォパパがろくに働かず借金ばっかりするへたれだったので、それを反面教師にオコンクウォさんはがんばってきたのである。まあ、いまの社会ではアッという間にDVで豚箱に叩き込まれるところだが、ウムオフィアではそれが正当なことだったのである。客が来たらコーラの実を割って歓迎し、巫女さんにはときおり神様がおりてきて、双子は悪しきものだから悪霊の森へ捨ててきなさいという、そんな社会なのだ。そんな社会なので、長老たちがオコンクウォさんに「お前の子供は殺すことにする」と宣告したときも彼は素直に従った。もちろん名残はあったが、その気持ちは彼にとって「弱さ」だった。弱さを皆に見せることを恐れ彼は自分で息子を殺してのけた。それ自体はまあいいんだが、そのあたりから彼の不幸が始まったのである。
というのも、村のお偉いさんの葬式に参加してるとき、うっかり彼のもつ銃が暴発してよそんちの坊主を殺しちゃったのだ。これはウムオフィアでは女型の殺人といって、7年間この地を去ればOKっていう罪だ。永久追放でないだけマシではあるが、村での出世街道驀進中だったオコンクウォさんはこのことをひどく厭う。なんでこーなっちゃうんだよー。だが彼は屈強な男なので、逃れた親族のもとでもしっかり働きヤム芋をたくさんこしらえて過ごす。たいした男である。さてそんなことをしてるうちに、ウムオフィアには白人の影が伸びつつあった。宣教師がやってきてキリスト教を広めたのである。ウムオフィアの人たちにも独自の信仰があるのでえらい反発されるが、その信仰の中で虐げられていた人々……大地の神が言ったからっつって子供を殺された連中や、生まれから迫害されていた階級の連中はキリスト教に改宗していってしまう。やがてそうでない人々も……。オコンクウォさんがウムオフィアへ帰ったころには、もうそこはかつてのウムオフィアではなく、男たちは神々を冒涜せしキリスト教会を叩き潰してやろうって気概もない骨なしチキンになってしまっていた。白人たちは一族を固く結びつけていたものにナイフを入れ、ばらばらにしてしまったのだ。
白人たちは武力で彼らの法をウムオフィアに押し付け、人々を投獄し、釈放料を求めた。オコンクウォさんはひとりで白人に立ち向かったが、続くものは誰もいなかった。彼は、白人たちにも、ウムオフィアにも受け入れられない人間となってしまった。彼は首をつって自殺。ウムオフィアのルールで、自殺したものは一族の地に埋葬されることはできない。一族に殉じようとした男は、一族のもとに還ることもできないのだった。
●
俺も現代人のはしくれだから、ウムオフィアのルールはマジいかれてんなと最初は思った。けど、連中が楽しそうにコーラの実を割ってたり、ヤム芋を溜め込んだり、結婚の儀で意味不明ではあるもののなんか歴史があるっぽい儀式とかやってんのみると、なんとなく望郷的な思いになって、ウムオフィア社会がちょっと輝いてみえた。その人々が、最後白人によって「ニジェール川下流域における未開部族」という一言のもとに切って捨てられるところ、めちゃめちゃゾクッとした。「未開部族」って。このゾクッはあんまり経験なかったものなんで、今回はいい読書だったと思う。
ぶっちゃけ、かけ離れた文化ってファンタジーみたいなものだからな、今思えばあの望郷の思いはファンタジー世界に対する羨望と同種のものだったかもしらん。
この作品で表現されてるのは、欧米諸国とキリスト教がどうアフリカの人々の生活と習俗を破壊していったかの描写だろう。ただ、破壊とはいってもキリスト教の入り込む余地ってのはもともとたくさんあったんだよな。全編にわたり、ウムオフィア社会の習俗に対する人々の不満点はちょくちょく書かれていたわけだし。双子は不吉とされてるから殺せ! とかな。そういう描写は全部キリスト教侵入の伏線になっていたといえる。であれば、最後白人社会の到来によってその伏線が全部回収されたことになるわけで、それも読後のすっきり感につながっているんだろうな。
文章はとても読みやすかった。話の流れも理解しやすい。現代とは全然ちがう文化の生活を描いているだけに、まったくなじみのない風俗や単語が出まくるんだが、同量の注釈がそのページ内に付されてるんでわかりづらいことがまったくなかった。翻訳者さんは長いこと注釈を付すか否か迷ったそうだが、俺は楽しめたと言っておくぜ。
翻訳者さんによる後書きにこんなこと書いてあった。翻訳作業中、「アチェベがいま、日本語でこの小説を書いたらどんなふうになるか」、この言葉がつねに立ち返るべき原点となっていた、と。うんうん、どんな作業を行うにしてもこういう一本の柱があるのはよいことだよな。いい文章でした。