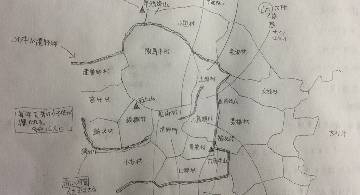●
この本はガキの時分トライしたことがあるのだけど、途中でリタイアしたんだよ。全然楽しめなくて。読むのやめちゃったの。だけれど、読書体力がついた今ならば! と今回読んでみたらあっさり読了できちまった。三週間かかっちゃったけれどね。サマリと感想を書く。
●
無名の猫「吾輩」は野良猫をやっていたが、ひょんなことから教師をやってる珍野苦沙弥さんちに住むことになる。そんなにいい環境でもないけれど、欲をいっても際限がないからこの家を終の棲家と定めることにする。
これがわりと賑やかで、同級生の迷亭や教え子の寒月くん、その友達東風くんがたびたびやってきて喋り倒す。金持ちの金田に嫌がらせを受ける事件があり、泥棒が入って山芋を盗まれる事件があり、隣の学校の生徒に野球ボールを打ち込まれる事件があった。哲人の独仙は警句を語り、同級生鈴木の籐さんは金田の指示で苦沙弥をスパイしにやってくるし、苦沙弥さんの娘たちはいつも騒がしい。
そんな生活を眺めていると、猫と比べて不合理な人間にも愛着が出てきて、面白い経験ができることにも感謝の念がわくものだった。そんなある日のこと吾輩ちゃんは客の残したビールを舐めて酔って水瓶に落ちて死んでしまう。けど、真の太平というのは死ぬことでしか得られないと悟っていたから、安らかに逝ったようだ。まあよかったよね。
●
いやあ普通に笑い声が出るレベルのギャグ満載の物語だった。なんというかな言い回しが面白いんだよね。語り手である猫はとかく客観的で人間を滑稽に思っているから地の文が自然笑えてきてしまう。苦沙弥先生たちのやり取りもギャグとして笑けちゃう。たとえば暑い日のやりとり
- 迷亭「丈夫な人でも今日なんかは首を肩の上に載せてるのが退儀でさあ。さればといって載ってる以上はもぎとる訳にも行かずね」
- 吾輩「と迷亭君いつになく首の処置に窮している。」
- 吾輩「吾輩は両君の談話を聞いたのである。聞きたくて聴いたのではない。聞きたくもないのに談話の方で吾輩の耳の中に飛び込んで来たのである。」
同じく尊大な様子で銭湯を覗きにいった猫内部の荒唐無稽を改行なしでひたすら描写するところもシュールで面白い。このシーンで面白かったのが、銭湯のはしっこにおすわりして目をぱちくりさせながらじーっと大人しくしている猫の姿が目に浮かぶことだ。この小説ってわりとそういうとこ、あって、猫が喋るからといって決してその行動が虚構の猫らしからないのだよ。
苦沙弥先生と猫のコンビでは次の行がまったく好き。
- 苦沙弥「いやそういう事は全くあるよ。僕は大学の貸費を毎月々々勘定せずに返して、しまいに向から断られた事がある」
- 吾輩「と自分の恥を人間一般の恥のように公言した。」
でもやっぱり良いのは迷亭君だろう。たぶん猫も彼が一等気に入りなんじゃないかな。
- 吾輩「人のうちへ案内も乞わずにつかつか這入り込むところは迷惑のようだが、人のうちへ這入った以上は書生同様取次を務めるから甚だ便利である。」
- 迷亭「ちょっとこの白をとってくれ玉え」 独仙「それも待つのかい」 迷亭「ついでにその隣りのも引き上げて見てくれ給え」 独仙「ずうずうしいぜ、おい」
- 迷亭「どうにもいい手がないね。君もう一返打たしてやるから勝手な所へ一目打ち玉え」 独仙「そんな碁があるものか」
- 迷亭「独仙君いい加減に切り上げようじゃないか」 独仙「まだ片付かない所が二、三箇所ある」 迷亭「あってもいい。大概な所なら、君に進上する」 独仙「そういったって、貰う訳にも行かない」 迷亭「禅学者にも似合わん几帳面な男だ。」
終盤、総大成のように仲良し組が苦沙弥先生の家で喋り倒すシーンは雰囲気が大好き。
- 東風「夜通しあるいていたようなものだね」 迷亭「やれやれ長い道中双六だ」 寒月「これからが聞き所ですよ。今までは単に序幕です」 迷亭「まだあるのかい。こいつは容易な事じゃない」 寒月「ここでやめちゃ仏作って魂入れずと一般ですから、もう少し話します」 迷亭「話すのは無論随意さ。聞く事は聞くよ」 寒月「どうです苦沙弥先生も御聞きになっては。もうヴァイオリンは買ってしまいましたよ」 苦沙弥「こん度はヴァイオリンを売るところかい。売るところなんか聞かなくってもいい」 寒月「まだ売るどこじゃありません」 苦沙弥「そんならなお聞かなくてもいい」 寒月「どうも困るな、東風君、君だけだね、熱心に聞いてくれるのは」
●
この話でも「人は石である」理論の妥当性を感じた。「自分と異なるものには腹が立ちづらい」って理論ね。この話っていじわるな連中とか性根のアレな連中が出てくるのだけど、吾輩ちゃんの地の文からは、それによって気分を害した様子とかが伝わってこないのだよ。それはまったく妥当なことで、吾輩ちゃんにとって人間って全く異なるものであり、異なるものってのは基本的にどうだっていいのだ。俺が人に感じている「石」感よりも強い「石」感を我輩ちゃんはもっていることになる。だから吾輩ちゃんは人間に苛立ったりしないし、客観性を持ち続けられるのだ。それをちゃんと文章で表現できている夏目漱石はやっぱスゴいと思うぜ。
●
実のところ読みはじめのころは、物語の主軸が見つからなくて読み方を定めるのに難儀した。でもそのうち分かった。これはシットコムのようなものなんだな。共通の登場人物が、状況と場所を変えて面白おかしく喋り倒す、それを楽しむものなんだ。それでFRIENDSでいうところのCentral Perkが珍野宅ってわけだね。そうしてみると迷亭君が蕎麦を食ってるシーンに寒月君がやってくる描写なんて、Central Perkでチャンドラーとジョーイが喋ってるところにフィービィがやってくるようなところを彷彿とさせる。
- 我輩「ところへ寒月君が、どういう了見かこの暑いのに御苦労にも冬帽を被って両足を埃だらけにしてやってくる。」
蕎麦で思い出したが、ガキの時分のみどりんがわさびを食べられるようになったのって、このシーンのお陰だったんだよ。確かこのシーンのちょっとあとでリタイアしたのだけど、このシーンで迷亭君が蕎麦を食ってるのがとても美味しそうだったもので、そのときから蕎麦にはわさびを入れるようになったんだった。今回の読書では期せずしてこの思い出のシーンに出会えたのも楽しめた。
てか何俺当たり前のように迷x独とか言ってんだ!? ルームメイトの影響だ!
●
(2017.02.12.追記)
おっと大事なことを書き忘れていた。内容に関することじゃあないのだけど、今回の本は脚注がまとめて巻末についているタイプだったが、これはとても参照しづらく快適な読書に障る。いやこういう形式の本のほうが多いから、これだけ見たら文句も言わないのだけど、『崩れゆく絆』という俺にとって理想的な脚注の本を経験しちゃっているもんで。